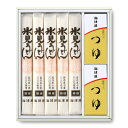富山県氷見の特産品「氷見うどん」。
この記事では、氷見うどんの食べ方や実際の味などを写真付きで紹介します!
富山名物「氷見うどん」についてまとめてみました!
関連記事
- 【割引クーポンがお得】
-
楽天トラベル割引クーポン
-
氷見うどん|通販がオススメ


氷見うどんは、インターネット通販でも購入できます。
ギフトや贈り物で県外に送るときにも、通信販売は圧倒的に楽で安いので便利です。
氷見うどんでよく見かけるのは、次の3社の商品。
- 海津屋 (かいづや)
- 高岡屋 (たかおかや)
- 美濃屋 (みのや)
特に海津屋のうどんは、かなり有名です。
海津屋
富山県内のお土産屋で一番見かける氷見うどん。
高岡屋
富山の氷見うどんの元祖。
美濃屋
リアル店舗の「氷見うどん屋」で見たことがあるので、一度食べてみたいです。
氷見うどん|食べ方


氷見うどん (細麺) の食べ方の手順は、次のとおりです。
- 沸騰した2.5リットル以上のお湯に麺をほぐしながら入れる
- 中火で6~7分茹でる
- 冷水で水洗い
- (温かいうどんを食べる場合は) 再度温める
湯で時間が多少長いくらいで、あとは通常のうどんや蕎麦と同じです。


富山県氷見の特産品「氷見うどん」の細麺 (海津屋)。紙のような質感のパッケージに入っています。


細麺といっても、3~4mmと蕎麦などよりは太いです。
湯で時間は細麺でも6~7分とラーメンや蕎麦よりも長時間必要。


茹でていると、麺が透き通った感じなってきます。
あとは、冷水で水洗いして〆てコシを出せば完成です。
氷見うどん|食べて比べてみた


氷見うどんは、冷でも温でもどちらで食べても美味しいです!


氷見うどんの温かいのと冷たいの、どっちが好きかを投票してみた結果。
半々でした!
僕は冷たいの派だったのですが、今回の食べ比べてどちらも美味しいことに気づいたので納得の投票結果です。
温かい氷見うどん


氷見うどんは、普通のうどんのように温かいまま食べても美味しいです。
僕は、シンプルに白だしと玉子で食べるのが好き!
家にとろろ昆布があるときは、乗せると1段階グレードアップします。


富山県民は、とろろ昆布が大好き。
温かい汁に溶けてとろけた昆布と、氷見うどんが絡むと最高です!
冷たい氷見うどん


氷見うどんは、そうめんや蕎麦のように冷たいまま汁につけて食べても絶品です。
茹で上がった麺を冷水でしめてそのまま食べるので、コシの強さをより感じられます。
氷水で一気にしめるのがオススメ!


温かい氷見うどんも美味いのですが、僕は冷やして素麺のように汁につけて食べる方が好きです。
シンプルですが、ツルツルシコシコで喉越しもよいのでかなり美味しいです。
氷見うどんとは?


氷見うどんは、富山県氷見市の郷土料理。
人気ゲームアプリ「パズドラ」にも登場しています。
ここでは原料やカロリーのほか、ルーツなども紹介していきます。
日本三大うどん
氷見うどんは、日本三大うどんとも呼ばれることがあるうどんです。
長崎県の五島うどん、群馬県の水沢うどん、富山県の氷見うどんで、日本五大うどんと呼ばれることもあります。
特徴は、コシのある麺。手打ちではなく手間がかかる手延べで作られています。
由来などについては、Wikipediaに次のように書かれています。
作り方は稲庭うどんと同じで竹によりながらかける手縫いで、油を塗らない。ルーツは輪島のそうめんで、1751年(宝暦元年)に「高岡屋」が輪島から技法を取り入れて作り始めたとされる。元々は「糸うどん」との名称で、他の手延べうどんとは異なり、最後まで手で撚りをかける特徴があり、高岡屋においては『一糸伝承』の名で現在も販売されている。このうどんは加賀藩御用達のうどんであり、商品名の通り製法は家伝のものであった。なお、かつて高岡屋では「手打」の表記を採用していたが、これは周辺に類似する製法がなく、市販のような機械製麺ではないとの意味であり、切って麺にしているわけではない[1]。 現在氷見うどんと呼ばれるうどんには、こうした伝統的なものと、手延べによるものの2種類があり、高岡屋では両者が販売されている。一般的な手延べうどんの場合、麺が折れにくいようあえてコシを出さない場合が多いが、氷見うどんは両者ともに生地に対して力を加え練り上げるため、手延べの滑らかさと手打ちのコシを共に具有している特徴がある。
引用:Wikipedia
原材料やカロリー


氷見うどん(細麺)の原材料はこんな感じです。
原材料はすごくシンプルで、小麦粉・食塩・打ち粉のみ。


氷見うどん (細麺)のカロリーはこんな感じです。
1束200gなので、1人で全部食べる場合はこの数値を倍で考えればOK!
1人でも食べられる量ですが、気持ち多いかなぁ…といった感じの量です。
氷見うどん事件とは?


今回調べてみるまで全く知らなかったのですが、2007年に「氷見うどん事件」という問題が起こったそうです。
ざっとした内容は、次のとおり。
氷見うどん高岡屋本舗が、岡山県で製造したうどんを「氷見うどん」として販売していました。
「氷見うどん」の商標を持っている海津屋が、それについて不正競争防止法に基づき訴訟を起こし、億単位の賠償金で勝訴したというもの。
もっと詳しく知りたい人は、各々調べてみてください。
氷見うどんの比較 (海津屋&高岡屋)


氷見うどんは、会社ごとの違い (海津屋・高岡屋・美濃屋) のほかに、麺の太さごとにも多くの種類があります。
- 太麺
- 半生太麺
- 細麺
- 極細麺
- 氷見素麺
- そば
全て比べることはできなかったので、今回は海津屋と高岡屋の細麺を比較してみました。
海津屋


海津屋の氷見うどん細麺。
内容量は200g、販売価格は税込500円強です。


細麺といっても、麺の太さは一般的なうどんと同様です。
高岡屋


高岡屋の氷見うどん。
内容量は180g、価格は税込500円強。


糸うどん細麺というだけあって、気持ち海津屋よりも細いです。
ただし食べてみた感じだと、僕程度の感覚ではほぼ違いが分かりませんでした…
明確な違いは、20gの内容量と麺の若干の細さだけかも…
まとめ


富山県氷見市の名物「氷見うどん」についてまとめてみました!
気軽な気持ちで調べてみたら「氷見うどん事件」などがあったことや、「氷見うどん」が商標なことも知れて新しい発見がありました。
氷見うどんは乾麺なので日持ちもします。
自宅用に加えて、富山県外の家族親戚友人にギフトとして送るときっと喜ばれるはずです!
あわせて読みたい
- 【割引クーポンがお得】
-
楽天トラベル割引クーポン
-